
ePublishingPort が主催する「セミナー名」が8月27日に東京・渋谷にて開催されました。そのレポートをしてみたいと思います。
詳細は以下に。
「Qlippyが創る、書籍を活かす新たなコミュニケーション」
第一部は「Qlippyが創る、書籍を活かす新たなコミュニケーション」というテーマで、株式会社スピニングワークスの代表取締役 白形 洋一さんによるセッションが行われました。
「Qlippy」は7月に発表されたソーシャルリーディングサービスです。iPadアプリ(iTunesが開きます)とWebサイトが連携していて、自分のページをサイト上に登録。そしてそのページに自分の所有している電子書籍の登録や、自分が気になるところをクリップして、その情報を共有するということも可能です。
白形さんのお話の中では、ユーザー同士、ユーザーとコンテンツの双方に利益が出るような仕組みを作りたいということで、今回のQlippyを企画されたそうです。デザイナー、開発者、白形さんの3人が飲み屋で「おもしろいものをつくりたいよね」という話の中からQlippyが生まれたという誕生秘話や、Qlippyを出版社に売り込む際の苦労話など、普段、一般の方には聞けないお話が多く、とても興味深いお話になりました。
「Qlippyによってどうやって読書が変わっていくか?」というお話では、コミュニケーションの双方向化(読者と出版社、もしくは著者本人との双方向化)をあげていました。今後はビジネスモデルとしてフリーミアム、そして読者からのアフィリエイト、蓄積されたデータからのリサーチサービス、システムのOEMなども計画に入れているそうです。
質疑応答では「Webサービスと連携したアプリを出すときに、appleアプリの審査に心配はなかったのか?」「ソーシャルメディアとしての蓄積されたデータはどう見るか?」「アプリのダウンロード数は?」「Qlippyの開発費は?」など、普段聞けないようなことを突っ込む参加者も多く、会場内でも笑いが出ていました。
「どうする?どうやる?どうなる?出版社によるメディアの活用と収益化」
第二部はパネルディスカッション形式で「どうする?どうやる?どうなる?出版社によるメディアの活用と収益化」というテーマで行われました。
テクニカルライターの山口真弘さんがモデレーターをつとめ、パネラーは、第一回に引き続き、株式会社スピニングワークス 代表取締役 白形 洋一さん、ターゲッティング株式会社 代表取締役 藤田 誠さん、そして某広告代理店のBさん(諸事情により名前は伏せさせていただきます)の4人でディスカッションが行われました。
自己紹介のあとに、本題にはいりました。ディスカッション形式だったので、かいつまんで質問、回答を羅列していきます。
「出版社の中でもネット部署と編集部との熱意(温度差)はあるのか?」
- S社を例に挙げて「編集部とネット部署の距離が近いところは、お互い熱意が高い」ということ。
「出版社によって、アプリ開発社とのやりとりはどうだったか?」
- 出版社によってさまざまで、好意的なところもあれば、そうでないところもあり。
- 本の厚みを気にしないで出版できるという喜びができたという方も。
- コンテンツによってはDRMはかけないという所もあった。
「人気雑誌のネット活用方法」
- ターゲットは誰か? 競合は?を改めて考える
- 女性ファッション誌などでは、媒体によって競合が変わる。
- 実は女性ファッション誌の競合は雑誌ではなく、アメーバブログだったりする
- 既存メディアとブログとの連動活用方法
「だれもが個人メディアとして世の中に出られる状況の中で、どうやってメディア活用をしていくか?」
- 出版社と編集プロダクションとの違い
- 電子書籍は有料メールマガジンでもいいんじゃないか?本を売るのではなく、コンテンツを売るということを忘れていないか?
- マンガでソーシャルっていうのはどうなんだろう?
- 雑誌をキーにして、コミュニティを作る機能(売ります買います、サークル募集ページなど)あったけど、今ではmixiなどのコミュニティに流れていくこともあるんじゃないか?
- 雑誌にはインフォメーションメディア、ライフイベントメディア、ライフスタイルメディア。その個々のメディア(雑誌)によってコミュニティが作られてきた
- 紙媒体とデジタル媒体の収益の違い
「雑誌とネットでの広告の打ち方の違いは?」
- Qlippyを学術書の読み方、考え方をシェアするのはどうだろう?
- そんな中で広告を打たれても…と思う人もいるのでは?
- Twitterとgoogleとのマネタイズの関係
- オーディエンスデータ解析技術を使っての広告の打ち方
- 広告を広告のように見せない誘導の仕方があるんじゃないか?
「雑誌の編集の形がいろんな表現の方法があってもいいんじゃないか?」(ソーシャルニュースサイトと雑誌編集者の方とのやりとりがありました)
- ソーシャルニュース的な雑誌を作ってもいいんじゃないか?
- 実は去年のTIMEでそのような実験をやっていた。結果、失敗したとのこと
- 「雑誌」は、雑誌自体のブランディングがあって「編集長」がしっかりとブランディングすることが今後も必要になる。
- 本のセレクトショップがあると仮定して、その店の店長がブログやソーシャルメディアという考え
- セレクトショップはなくなっても、本(コンテンツ)自体はなくなることはない。
- 雑誌のテーマごとで抽出して、新しくパッケージングをすることだけが正解じゃない。
…といった、後半は参加者同士の熱い語らいもあり、とても楽しいディスカッションになりました。
コンテンツをどのように生み出すのかも大事ですが、どうやったらよりそのコンテンツに価値が見いだせるのか?その結果、どうやったら収益に繋がるのか?コンテンツに関わる方全員で、一度議論してみてはいかがでしょうか?
といった感じに、今回もePublishing Cafe、とても面白い内容になりました。次回は今月中(10月)に開催の予定なのでで、日時等が決まれば公式サイト、もしくは公式Twitterアカウント(@epubport)でご連絡しますので、興味のある方はこまめにチェックをお願いいたします。
最後に
今回のイベントの中で私の一番印象に残った言葉は、白形さんのお話された言葉で「私たちはコンテンツ自体を扱うのではなく、コンテンツにどのような付加価値をつけていくか?」という言葉でした。
「電子書籍」という媒体は、紙媒体とはまた違った付加価値を付ける方法が今後、新たに開発・発表されていくことだと思います。とかく「電子書籍」という単語、フォーマット、作り方のみにフォーカスされて「電子書籍を作った後にどうする?」ということが忘れられているような気がします。制作サイドとしては電子書籍を作る工程を把握しておくことは必要だとは思います。ですが、もう一歩踏み込んで「電子書籍を使ってどうしたいのか?」を考えて行動することが見えてくれば、新しい自分のやりたいことやビジネスモデルが見えてくるのだと思います。メディア活用とマネタイズ、もう少し自分にとっても考えてみたくなったイベントでした(^^)
【関連サイト】
✓ePublishingPort (epubport) on Twitter(公式Twitter)
最新記事 by 杏珠(あんじゅ) (全て見る)
- メインOSをmacOS Sonoma(ver.14)にバージョンアップしました - 2024 年 6 月 19 日
- 新しいMacを購入&無事にセットアップも完了!【Mac mini (2023)購入までの道 その3】 - 2024 年 1 月 13 日
- 新しいMacをどれにしようか悩んだ結果【Mac mini (2023)購入までの道 その2】 - 2023 年 7 月 23 日




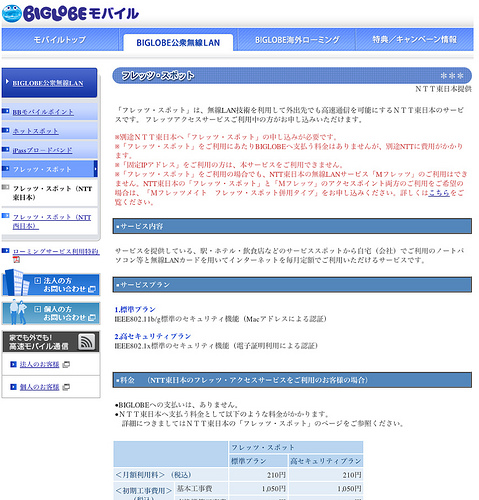
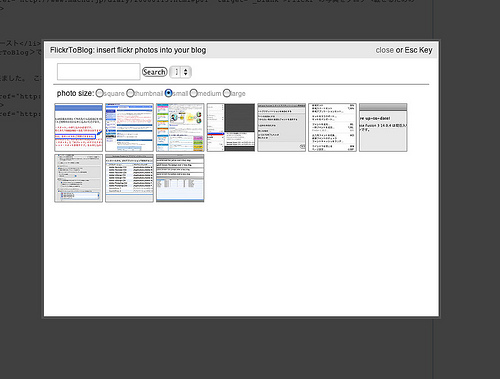
コメント